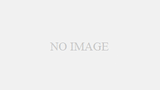株高不況の現状とその要因
新型コロナウイルスの収束後、日経平均株価はかつてのバブル期を超える勢いで上昇し、多くの投資家が歓喜しています。
しかし、その一方で、生活者の実感として「好景気」と感じている人は少ないようです。
このギャップはなぜ生じているのか、そしてそれが「株高不況」と呼ばれる現象の根幹にあるのです。
日経平均株価が高値をキープしているのは、企業の収益性や投資家の期待感が反映されていることもありますが、それだけではありません。
背景には、過去のトランプ政権時代の関税政策を経てもなお持ち直してきた世界経済の構造的変化があります。
それらの要因を詳しく見ていきます。
株価の上昇は、企業の収益が上がっていることを示す一方で、これは必ずしも労働者の賃金上昇につながっていません。
グローバル化が進むなかで、多くの企業は安価な労働力を求めて海外に生産拠点を移し、国内の雇用拡大や賃金上昇に繋がりにくい状況です。
さらに、企業が利益を上げるためには、必ずしも従業員の待遇改善が必要ではないという構造も問題です。
こうした背景から「株高不況」という言葉が浮上してきます。
現在の生活者が置かれている厳しい状況
一方、生活者の視点に立つと、物価の上昇や賃金の停滞が続き、家計はますます厳しい状況です。
特に、この数年で電気代やガソリン価格の上昇が目立ち、家計を圧迫しています。
こうした物価高の理由の一つには、エネルギー価格の高騰や物流の乱れがあります。
エネルギー価格が上昇すると、生活のあらゆる分野でコストが増加するため、物価全体が押し上げられます。
また、国内総生産(GDP)の成長が基本的に低調であることも、賃金が上がりにくい背景の一つです。
労働市場では、実質的な雇用環境は改善されても、高度なスキルを持ち合わせない労働者には依然としてチャンスが少なく、これも所得の増加につながっていません。
さらに、円安による輸入価格の上昇も直接的な家計への打撃を与えています。
このように複数の要因が結びつき、庶民の生活を圧迫しているのです。
対策としての投資戦略
こうした状況下で、生活者が自らの生活を守るためには、やはり「投資」という選択肢に目を向ける時期に来ているのかもしれません。
投資とは決して大規模な資産を動かすことだけを指すものではなく、小規模でも資産の運用を始めることが可能です。
近年では、金融教育を受け、小口投資を始める若者も増えてきており、株式投資やインデックスファンドのような長期に渡る運用が注目されています。
株高不況の状況下で、「株価だけ」を頼りにするのではなく、地に足をつけた資産運用が必要です。
たとえば、投資信託やETFを活用し、リスクを分散する方法があります。
これらは、個人で銘柄を選ぶよりもプロが運用してくれるため、比較的安全に資産を増やすことができるとされています。
また、デジタル通貨の導入やNFTといった新しい投資手段も広く開かれています。
こうした選択肢を情報収集し、知識を深めてから慎重に取り組むことが重要です。
金利の動向にも注意を払う
投資するにあたって、金利の動向も注視する必要があります。
利率が上がれば、預金や債券の価値も増えやすいため、保守的な投資先としての選択肢が広がってきます。
同時に、借入金がある場合はその金利にも気を配らなければなりません。
金利が急激に上昇する局面では、借入している資金に対する圧迫が大きくなり、資金繰りが難しくなることもあります。
一方で、低金利政策が継続される状況下では、不動産投資や設備投資を狙うことで、資産を増やす可能性を探ることもできます。
しかし、それには市場の動向をしっかりと把握し、多角的に分析することが必須となります。
特に、日本の金利は低く抑えられているため、海外の状況も視野に入れながら戦略を立てることが賢明です。
消費を見直し、生活スタイルを変える
消費者としての見直しも重要です。
多くの場合、無駄な支出は生活を圧迫します。
家計を見直し、いかに賢く消費していくかが問われています。
物価高騰の影響を受けつつも、普段の買い物を工夫したり、必要ない商品やサービスを購入しないことが、小さな積み重ねでも大きな効果を生み出すことがあります。
例えば、日常の交通手段を見直すことで、ガソリン消費量を減らしたり、サブスクリプションサービスを整理して不必要な支出をカットしたりすることが考えられます。
こうした生活スタイルの小さな変化は、長期間にわたって生活費を削減し、経済的な余裕を生む可能性があり、結果として投資に回せる資金を増やすことにもつながります。
まとめ:新しい生活のためのポイント
今回の記事を通じて、株価が上昇し続けても、生活者の実感に影響を与えない「株高不況」の背景と、その対応策について考えてみました。
大切なのは、現状を正しく理解し、自らの生活を豊かにするための一歩を踏み出すことです。
これらのポイントを心に留め、現代の生活と経済状況にしっかりと適応することが重要です。
実体経済と金融市場が必ずしも一致しない日本経済ですが、そのなかで生き抜くための考え方をぜひ取り入れてみてください。