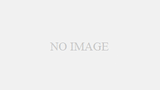豊かな自然に抱かれながら、丹精込めた畜産経営を実現する。
上垣康成さんが執筆した『自分が食べるものは自分で生産したいと願う、但馬牛農家の経営哲学』は、ただのビジネス書ではなく、農業を基盤にした新しい生活の形を提案する心温まる一冊です。
山間地での生活を満喫しながら、しっかりと収益を上げるための知識と技術が詰まったこの本には、畜産という仕事の魅力や課題、そして考え方が凝縮されています。
少頭多畜種の加工経営に至るまでのストーリー
但馬牛を中心に繁殖和牛経営を行ってきた著者、上垣康成さんの視点から始まる本書。
和牛繁殖経営から、少頭の多畜種加工経営へと移行するまでには、多くの試行錯誤が重ねられてきました。
なぜ多畜種加工経営へと転換を図ったのか、その理由は非常にシンプルでありつつ、深く考え抜かれたものです。
一つの商品だけではなく、多角的な商品展開を行うことで、様々なリスクを回避すると同時に、消費者の多様なニーズに応えることができると考えました。
牛や豚、アイガモを自分の手で育て、自らの手で加工して提供する、そのプロセス自体が商品の付加価値となるのです。
この一連の流れには、作り手としての喜びが詰め込まれています。
小さい畜産の魅力とは何か
従来の大規模畜産とは異なるアプローチとして注目を集める少頭多畜種の畜産。
上垣さんはその魅力を存分に語っています。
大規模経営にはない利点として、何よりも畜種それぞれに深い愛情を注げること、すべての生き物に対してしっかりと目が届くことが挙げられています。
そうすることで、健康的な育成環境を提供できるとともに、病気の早期発見や、畜種ごとの特性に応じた適切なケアを施すことが可能になります。
小規模であればあるほど、家族経営の利点を生かし、効率よく資源を活用し、コストを抑えた生産が可能になります。
畜産から精肉加工へと進化するプロセス
畜産農家としてのノウハウを活かしながら、精肉加工を自社で手がけることの利点を本書で詳述しています。
まず第一に、自分たちが育てた命を、自分たちの手で最後まで見届けるという、信念に基づく精神があります。
そして、消費者に対しての信頼を確立することも大切です。
自分たちの手で管理し、加工することで、品質には絶対の自信を持ち、正真正銘のおいしいお肉を提供できるのです。
本書では、その加工のプロセスから必要な機器、許可の取り方まで、初めての方でも分かりやすいように具体的な方法が詳述されており、実践的な指南書としても高い価値があります。
販売戦略としての多様性と創意工夫
ただ品質の良い商品を作るだけでは消費者に届きません。
そこで、上垣さんの取る販売戦略が極めてユニークです。
ネットを活用した日常の発信から、作った商品をどのように市場に送り出すか。
そして、それを消費者の目にどのように映らせるか、このすべてが販売のプロセスとして語られています。
徹底して自らのこだわりを貫きながら、自身で店舗を持つことによるブランディング戦略や、セット商品として魅力的に提供する方法など、消費者の立場に立ったサービスの具体的な展開が新たな学びを提供します。
小さい畜産を支える哲学と経営方針
本書の根幹を成すのは「できるだけ自分でやる、時間をかける」という考え方です。
現代のスピード社会の中で、あえてじっくりと時間をかけた経営や生産プロセスを選択することで見えてくる世界があります。
これは、単にビジネスを成功させるためのノウハウではなく、一人ひとりが心豊かに充実した生活を楽しむための哲学でもあります。
また、農家としての強みを活かし、地域との結びつきを重視し、補助金に頼らないことで独自の経営スタイルを維持する姿勢は、これからの農業を考える指針ともいえるでしょう。
命をいただくことの意味を伝える活動
最終章で著者が説くのは、「命をいただいていることを伝える」という活動の重要性です。
特に現代では、消費者が「お肉がどこから来るのか」を知らずに暮らしていることが多々あります。
牧場見学や、アイガモの解体体験を通じ、消費者に実際に命を感じてもらう機会を提供することで、その裏側に潜む命の大切さを伝えています。
この活動は、単なるビジネスとしてではなく、人としての生き方を見つめ直す貴重な取組みとして、農業の新たな可能性を示唆しています。
このように『自分が食べるものは自分で生産したいと願う、但馬牛農家の経営哲学』は、ただ商品を作るだけでなく、その背後にある一つ一つのプロセスに込められた情熱と哲学を余すところなく伝える内容になっており、農業に興味がある方はもちろん、食について考えたい方にとっても必読の書と言えるでしょう。