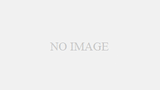お金の教育を見直す時代に、子どもたちに伝えたい大切なこと
現代は消費増税やキャッシュレス化の波が押し寄せ、私たちの生活は日々刻々と変化しています。
そんな中で、ふと思うのです。
私たちが子どもの頃、「お金」についてどのような教育を受けてきたのか、と。
お金というトピックは、社会においてタブー視されがちですが、お金に対する正しい知識や願望を持つことは、子どもたちがこれからの人生を形成する上で欠かせない要素です。
今回紹介するのは、八木陽子氏の「お金の教え本」です。
この一冊は、単なるお金の知識だけでなく、社会の見方や将来の生き方を考える一助になるでしょう。
物の価値を理解する子どもたちのために
お金教育の第一歩として重要なことは、「物の価値」を理解することです。
日々何気なく使っている物の値段はどのようにして決まるのか。
これは大人でも疑問に思うことが多々あります。
子どもたちは、ゲームやおもちゃを欲しがる一方で、その背景にある経済の動きはわかっていないことが多いので、本書ではこの物の価格の決まり方を丁寧に解説しています。
例えば、ある商品が高価である理由、それには生産コストや流通経路、そして需要と供給の関係が絡んでいるかもしれません。
こうした複雑なメカニズムを子ども向けにわかりやすく説明することで、自分が欲するものの価値を具体的に把握させることができます。
この理解は、ただ物を「欲しい」ではなく、「どうして欲しいのか」「そのために何が必要か」という考える力を育むでしょう。
未来を支えるキャッシュレスの世界とは
現代社会では、キャッシュレス化が進んでいます。
将来の子どもたちが生活する社会は、現金を持ち歩かなくても生活できる世界かもしれません。
この変化は、お金の本質を変えつつあります。
本書の「未来のお金」の章では、キャッシュレス化の流れとその影響について取り上げています。
キャッシュレスの利点は多々ありますが、そこにはメリットだけでなくリスクも伴います。
例えば、デジタルデータの扱い方、プライバシーの保護、お金のトラッキング能力の向上などです。
子どもたちには、簡単に支払える便利さと同時に、データセキュリティの重要性についても学んでほしいところです。
それによって、未来のキャッシュレス社会でのサバイバル力を身につけることができると考えています。
銀行の役割を知り、資産の安全性を考える
大人になっても理解しきれていないことが多いのが、「銀行の役割」です。
本書では、「銀行ってなにしているところ」の章で、銀行がどのようにして経済を動かすのかを解説しています。
単にお金を預けるだけの場所ではなく、融資やリスク管理、資産運用など幅広く社会に貢献していることを学びます。
最近の子どもたちは、デジタルバンキングの台頭によって実際に銀行窓口に行く体験が少なくなっています。
そのため、銀行の役割を知ることは、資産管理の基本を知ることにも繋がります。
また、銀行と同時に理解したいのは「信用経済」。
自分の信用によってどのように生活が変わるか、社会との関わり方を実感する機会にもなる一章です。
投資という選択肢で未来を考える
「投資」という言葉に、どのようなイメージを抱いているかは人それぞれです。
リスクが高い、難しいと感じる方も多いかもしれません。
しかしながら、資産を何倍にも増やす可能性を秘めているのが投資です。
本書の第四章では、この投資について子どもにもわかるようなシンプルな説明がされています。
投資の基本的な考え方、例えば「リスクとリターンの関係性」や「長期的な視点」などを持つことで、子どもたちは自ら未来の資産を築く道を見出すことができるかもしれません。
また、家族の中で一緒にこの投資について学ぶことで、コミュニケーションの機会となり、親子の関係もより良いものにする効果が期待できるでしょう。
税金や社会保障の役割を理解する
私たちが生活する社会は、学校教育、医療サービス、公共インフラなどによって支えられています。
これらのサービスの資金源として重要なのが「税金」です。
本書の第五章では、税金の役割や社会保障について詳しく紹介しています。
税金は私たちの生活の中でどう役立っているのか、子どもたちに具体的に伝えることで、彼らがしっかりとした納税者になるための基礎知識を提供します。
社会保障とは何かという問いに答えることで、私たちが社会の中でどのような形で支え合っているのかを理解することができます。
実体験を通して学ぶのが望ましいですが、このように理論的に学ぶことで、税金や社会制度が身近に感じられる助けになります。
これにより、未来の子どもたちはより良い社会を築く一員としての自覚を持つことができるでしょう。
まとめ: お金の知識が未来へのパスポート
今回紹介した本は、単なるお金の使い方指南書ではありません。
物の価値を理解し、キャッシュレス社会での生き方を考え、銀行の役割を知り、投資の可能性を探り、税金や社会保障を理解する。
これらを学ぶことで、子どもたちの視野が広がり、未来を自ら切り拓く力を養うことができるのです。
*お金*というテーマに対して、子どもたちが好奇心を持ち、一歩踏み出して学ぶための最高の入門書です。
八木陽子氏が著したこの「お金の教え本」は、未来の選択肢を広げる素晴らしい一冊。
読み終わった後には、子どもたちは新たな視点と意識を持って、日々のお金との関わりを見つめ直すことでしょう。
この内容が、親子でのディスカッションのきっかけにもなることを願っています。